村上 まどか先生
誰もが生まれながらに心に持つ言語理解の仕組みを追究する中で、「ヒト」という存在の面白さを実感する。
村上 まどか
Madoka MURAKAMI
英文学科
専門分野?専攻/英語学、生成文法
Madoka MURAKAMI
英文学科
専門分野?専攻/英語学、生成文法

[プロフィール]東京外国語大学外国語学部英米語学科卒、同大学院 外国語学研究科ゲルマン系言語専攻修了。ハワイ大学マノア校大学院言語学科修士課程修了。熊本県立大学を経て、2005年に実践女子大学へ着任。
「どうしてこんな文が正しいの?」という思いから英文法の研究へ
本学の英文学科での学びは、大きく分けて「イギリス文学?文化」「アメリカ文学?文化」「英語学」の3領域が用意されている。この中の英語学とはどのような学問だろうか。「英語についての言語学として、文学や文化といった“英語からつくられたもの”ではなく英語そのものを探究する分野です。とは言え、英語が絡むものであれば音声から英語教育、などなど幅広く研究対象にすることができます」と英語学を担当する村上まどか先生は語る。
英語学の中で、村上先生が専門とするのが文法だ。先生が文法に関心を抱いたのは、中学時代にある文に出会ったことがきっかけだった。「英語の授業中、“騒がしくしないで”という意味の英文をつくる問いが出ました。私はその日、予習をしていなかったのか、当てずっぽうで“Be not noisy.”と答えたら、違う、と。それなら、と“Not be noisy.”としてみると、それも間違い。正解は“Don’t be noisy.”だと教科書に載っているのを見て、目を疑いました」—助動詞doとbe動詞を一緒に使う構文は、否定の命令文のみ。先生はその時、「どうしてこんな組み合わせが正しいのか」という疑問を抱いたという。高校時代には、“I demanded that she go to hospital.”(彼女は病院に行くべきだと私は迫った)という、主張を表わすthat節の中で原形が用いられる仮定法現在構文に出会い、また衝撃を受けたそうだ。「要するに、めずらしい用法に遭遇すると、英語の文法って一体どうなっているんだろう?と感じる。その疑問が、英文法を探究する原動力になっていったと思います」
20世紀後半は、「生成文法」という言語学の分野が有力であり、先生も生成文法を研究分野にしている。「これは学校で教わる文法規則を超えて、“その言語を母語とする人が心の中に備えている”言語規則の体系です。人は誰でも見たことも聞いたこともない文章をつくったり、理解することができますよね。生成文法の研究は、どうしてそんなことが可能なのかを探るものです」
ハワイ留学で懸命に学んだ日々が、その後の基盤に
 ハワイ大学留学中の先生を訪ねたお母さまが撮影した会心の一枚。
ハワイ大学留学中の先生を訪ねたお母さまが撮影した会心の一枚。「もちろん息抜きもしたけれど、留学中は人生で一番と言っていいくらい勉強しました。充実した、楽しい時間だった!」と先生。。
先生は長年、生成文法における「動詞移動」について研究してきた。「動詞移動とは、動詞と助動詞や否定辞との位置関係に影響を与える動詞の動きです。母語話者が心の中に持つ生成文法の規則によって、疑問文や否定文、命令文がどのようにつくられるかを研究しています」と先生は述べる。
動詞移動についてもう少し具体的に紹介すると、“She is a student.”という英文を疑問形にすると“Is she a student?”となる。つまり、be動詞isが主語sheの左側(文頭)に移動したわけである。しかし、こうした移動ができるのは、英語の場合be動詞と完了のhave助動詞だけで、一般動詞は移動できない。“She said so.”を疑問形にすると、“Said she so?”は誤りで、正しくは“Did she say so?”となる。だが、実は古い時代の英語では“Said she so?”というように一般動詞も文頭に出ていたそうだ。英語以外のヨーロッパ言語では、例えばドイツ語の場合“Sagte sie so?(=Said she so?)”のように、現在も一般動詞が文頭に移動する。こうしたことはなぜ起こるのか。ごく大まかにいうと、原因か結果かはわからないが、英語の場合は助動詞doができてから他言語とは違う形になったようだ、と先生は語る。「ではなぜ、助動詞doができたのか。動詞移動はフランス語やドイツ語、イタリア語など他のヨーロッパ言語でも起こりますが、それらとは異なり英語の場合、動詞の語尾変化が時代を経るにしたがってどんどん少なくなり、文頭に出ていく力がなくなってしまったからだ、とされています」
研究の結果、先生は英語において一般動詞が文頭に移動できなくなった理由を、「中英語期(12~15世紀)にMood(法—その文の内容に対する母語話者の気分や心持ちを表わす動詞の語形変化)を完全に失ったため」と考えるようになったという。「このように、自分なりの解答を持てるようになるまでが結構大変です。英語の仮定法を常に念頭に置きながら、英語史を紐解き、役に立ちそうな論文を手あたり次第に読んだりしているうちに、ある時ぱっとひらめきが来る。すごく難しい数学の問題を解けずに悶々としていたのが、ふっとアイディアが浮かんできて一気に解決する、そんな感覚に近いかもしれませんね」
現在、生成文法の動詞移動というテーマを柱に、英語はもちろんさまざまな言語を取り上げ世界各地の国際学会で発表もしている先生。しかし、生成文法を追究しよう、と心に決めるまでに紆余曲折があった、と振り返る。「生成文法には大学時代から関心を抱いていたものの、今一つつかみかねている感じがあって。一時期、この分野は諦めようかとも思っていました」しかし、ハワイ大学の大学院に留学したことで道が拓ける。「ハワイ大学は言語学?言語習得論の分野で定評のある研究機関。そこで、改めて基礎からみっちり学び直したんです。文を分析する練習問題に何度も繰り返し取り組んで、添削を受けて、クラスの皆でディスカッションも行う。そうしているうちに、“やっぱり生成文法は面白い!”と心から感じるようになって、この分野を追究しようと気持ちが定まりました」2年4カ月のハワイ大学での学びの期間は、自分にとって研究者としての基礎をつくる時間だった、と今も大切に保管してある当時の練習問題を眺めながら先生は微笑んだ。
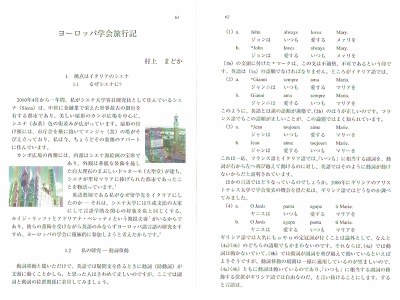 『実践英文学』に掲載された先生のヨーロッパ学会旅行記。
『実践英文学』に掲載された先生のヨーロッパ学会旅行記。イタリア語やギリシア語などヨーロッパ言語に見られる動詞移動を紹介しながら、リトアニアやポーランドを訪れた様子などを軽妙な文章でつづる。
インターネットで閲覧できる。
先述のように、動詞移動は英語よりむしろ、フランス語やイタリア語、ドイツ語といった他言語で見られる現象である。また英語ならではの特性を把握するためには、他言語の状況について理解しておくことも大切だ。従って研究が深まるにつれ、先生は対象言語の範囲を広げていった。幾つぐらいの言語を扱っているのか訊ねると、「ギリシア、リトアニア、ポーランド、オランダ、デンマーク…」と指折り数えて「10カ国語くらいですかね」と先生。1999年にイギリス、2010年にイタリアに留学し、英語のみならず欧州諸国の言語における動詞研究を行ったそうだ。そしてイタリアはもちろん、リトアニアやポーランド、オランダで学会発表したり、各国の学術誌に論文が掲載されたりもしたという。「学会が開かれる国の言語を対象に動詞移動の研究をして、それをその国で発表すると、聴衆から得られる手応えが深くてとてもエキサイティングなんです。2000年のギリシアでの学会の時に実感して、それから積極的にいろいろな言語を取り上げるようになりました。そもそも、1つの理論で多くの言語に生じている現象を説明できれば、その理論はそれだけ質が高いということ。自説の質を高めるためにも研究対象を広げていきました」
とはいえ、研究対象として取り上げた言語のすべてを使いこなせるわけではない、と先生は言う。「確かにイタリアにも留学しましたが、話せるのは片言。言語学者が研究対象の言語を話せる必要はなく、分析ができればいいんです」—先生が新しい言語を取り上げる時は、まず入門書を開いて動詞の活用形や仮定法?命令法、否定文や疑問文などにおける副詞と動詞の位置関係に注意しながら読んでいき、その後、対象言語の動詞移動に関連する論文を読む。それからその言語で文をつくって、母語話者に確認してもらったり、動詞移動の分析について質問したりするそうだ。
こうして多くの言語に触れた先生に、英語の特徴をどのようにとらえているかを訊ねると、「他のヨーロッパ言語と違って語尾変化が少なく、語順も比較的固定的で、外国語を学ぶのに慣れていない人でも習得しやすい」という答えが返ってきた。「もちろん、世界に影響力を持つイギリスやアメリカの言語であるという背景も大きいのですが、初学者に習得しやすいからこそ、英語がここまで世界に広がったのではないでしょうか」
その一方で、動詞移動をはじめとする生成文法の研究を通じて先生は、「ヒト」というものの面白さも感じる、と語る。「こうしてさまざまな言語を見ていると、語彙はもちろん異なることは山ほどあるのですが、反対に、いくつもの言語を通じて共通するものもある。生成文法の祖といわれるチョムスキーは、“ヒトに言語が使いこなせるようになるのは、裸で生まれた鳥のヒナが成長するにしたがって羽が生え揃い、空に飛び立つのと同じ”ようなものと言っています。世界中の誰もが自然と、自分が母語とする言語の規則体系を心の中に獲得できる。研究を掘り下げるほどに、ヒトの本質に触れるような感触があり、興味が尽きません」
「本気で取り組めるテーマ」を学生と一緒に探究
 2018年に行われたハワイ大学同窓会の様子を納めた記念写真とともに。
2018年に行われたハワイ大学同窓会の様子を納めた記念写真とともに。特に、恩師との再会は先生にとってとても感激した出来事だったとのこと。
主宰するゼミを先生は「英語に関する何でも屋」と称する。卒業論文の指導は、まず「本当に取り組みたいテーマ」を学生一人ひとりと模索することから始めるそうだ。「卒業論文のテーマを決める時期になると、学生はつい、“自分がやりたいこと”ではなく“うまく論文が書けそうなこと”に目が行きがち。でも、さほど関心がないテーマで研究をしても面白くない。ですから、最初は広く浅く話をする中で、その学生が本気で取り組めるテーマを一緒に追究していきます」—これまでの卒業論文の題目を見ると『ルイス?キャロルのアリスぎる言葉遊び』『フィリピンの英語—英語話者数世界3位の謎を探る』といった風に、学生が積極的にテーマを決め、のびのびと研究に取り組んでいた様子が伺える。テーマを定めた後は、アドバイスしながらも、「自分の力で」役立つ文献を見つけ、考察して、論を煮詰めていくようサポートするそうだ。そのようにして学生の主体性を伸ばして社会に送り出してあげたい、と先生は語る。
では、これから英文学科で学ぶ人、そして今学んでいる学生にも、先生からメッセージを。「できるだけ紙の辞書を使って!」教室でも電子辞書を利用する学生は多いが、単語を入力してぱっと出てきた意味を見て終わり、になってしまっていることが多いそうだ。「スクロールしたりして前後をじっくり読むことはあまりない。けれど、他の語義や用例、関連語句を目にすることで頭の中に知識が蓄えられていくのです。英語学が気になっている人はもちろん、せっかく英文学科で学ぶならばぜひ、中型以上の紙の辞書をせめて自宅では使ってほしいと思います」
それに関連してもう一つ。「語学の授業は(どちらかといえば復習よりも)予習に力を入れて!」予習の段階では間違って解釈したり、そもそも理解できなかったり、ということが起こる。それを授業で解決して「そうだったのか!」と気づいたり、納得してほしい。その積み重ねが実力になる、と先生は語る。「気づきや発見があると、学ぶのがぐんと楽しくなりますよ!」
ピックアップ授業!
女性と言語文化
言語が女性をどのように表象しているかという性差別の問題と、女性がどのような言葉遣いをするかという「女ことば」の両面から、言語と女性の関係を探る社会言語学の講義。「少女はなぜ自分を“ボク”と呼ぶのか」「現実よりフィクションで女性が女ことばを使うのはなぜか」といった切り口で授業を展開する。夫婦別姓推進派の担当者としては「婚姻と姓」のテーマに力が入るところ。オリジナルの「サザエさん一家の戸籍」を資料に、もしサザエさんが離婚したら姓はどうなるか、など日本の制度も解説する。
おすすめの本
以下2冊は、私が若い頃に読んで感銘を受けた、女性の生き方指南の書。
『裸足のシンデレラ』(木村治美、集英社)

1985年発行。古今東西の名作に登場するヒロインたちを分析した、感動的な書評集。木村氏は保守派の論客として知られ、自分とは意見を異にする点もあるが、文章の巧みさもさることながら、(本学ではないものの)英文学科で博士課程まで学んだ先達として見習うべきところの多い方だと思う。
『ニュー?ウーマン』(千葉敦子、三笠書房)

1987年発行。「いい仕事をして豊かに暮らす法」が副題。千葉氏の本はほとんど読んだが、「強烈な個性で人生を駆け抜けた」というコピーが別の文庫本の帯についていたと記憶している。45歳で乳ガンにより亡くなったジャーナリストによる、スマホやパソコンがなかった時代の生活術の書。キャリアや恋愛についての考え方は今なお新しく、人生にこれほど前向きで意欲的な女性がいたことに感服する。
※2018年10月 渋谷キャンパス研究室にて







